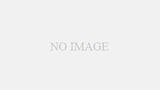またまた卓球の親バカ報告です。
だんだん自分でも鼻につくくらいになってきました。またかと思う方は閲覧を避けてください。がしかし、できれば寛大な気持ちでもって、ご相伴いただければ幸い至極に存じます。
娘の卓球のことは記録として残しておこうと思っております。オリンピック選手の可能性とかの素養はビタ一文これっぽちもない訳で、なので恐縮でしかありません。専門の方が閲覧したら、おそらく不愉快な気持ちになるのだと思いますが、閲覧する方が寛大な心でありますようにと祈り念じます。相すみません、ホントすみません。
先日、団体戦がありました。ここの管内で、選抜卓球選手権大会というのがありまして、全道大会まであります。2位までが全道にいけます。受験勉強のため3年生がどのチームにもいなくなり、ハードルが低くなったので、へたすると優勝するかなぁと思っていたら、本当に優勝しました。
最初の予選は総当たり3試合で、3-0、3-1.3-0 で、予選は1位通過、決勝トーナメントでは、勝てないだろうと思われていた常○中に準決勝で3-1、そして絶対に勝てないだろうと思われていた比○中に決勝3-1で快勝した。
勝因は何か? 最大の要因はやはり、娘の中学チームは娘達が入学した時、先輩がほとんどいなかったので、いきなり試合に出してもらえたことだろう。コテンパンにやられたりとかの試合の場数は圧倒的に多いため、接戦になればななる程、強さを見せる特徴がある。
また中学生の団体戦は、定員6人で戦わなければならないという規定があり、それに対してこうちの卓球部は部員が少ないので、オーダー表の出し方も工夫を凝らさなければならない。誰を先鋒にするか、誰を次鋒にするかなど、相手によって毎回順番を変えたりするのだが、6人制卓球の場合、このオーダー表の出し方で明暗が分かれることが多く、いわば丁半博打の要素がかなりあって実力以外の要素によって勝ち負けが逆転するケースはめずらしくない。特に実力が拮抗しているようなチーム同士では、ほとんどこのオーダー表の出し方で全てが決まってしまうといっても過言でない。昨年の中連の大会の際も、相手チームを甘く見て、オーダー表をあまりよく考えず無造作に提出してしまったため、結果、管内代表の出場を逃してしまうという手痛い失敗を経験している。
どのチームも全員が強い選手であるとは限らないためもあって、こちらが大砲の駒を出したつもりが、地雷の駒を踏んじゃったとか、などという感じそのもので、戦う前に提出するオーダー表というのは、昔の軍人将棋の駒置きに非常によく似ているのである。この駒置きは普通は大人の監督がやるのだが、娘属するチームは1試合1試合子供たちがやる。運動場の片隅で、1枚の「オーダー表」とタイトルされたB5番のホワイトペーパーを中心に置いて、うつぶせ状態の子もいれば(さすがに仰向けはいないが)、あぐらをかく子、とにかく皆で白い紙切れを真ん中に置き、喧々諤々と相手がどういう布陣でくるかを予想しながら、こちらは誰を出すとか、あるときは真剣に、あるときは、箸が転げてもおかしい年頃の女の子らしくのけぞって大笑いをしながら駒置き作業をする。このオーダー表に工夫をこらせるようになったこと、これも大きな要因の一つなのだろうと思う。
因みに高校生や大人の団体戦は4人集まれば出場できる、シングルスが4ゲーム、ダブルスは1ゲームの5セットマッチをやる。(最大5ゲームの3ゲーム先取、それは中学と同じ)。中学の場合は全員が違う人間が出なければならない。そのため定員が6人であるのに対し高校以上になると、シングルスが4人でダブルスはシングルスで出た選手がダブって出てもいい(むろん6人で出てもかまわないのだが)、そのため4人で出場するケースが多い。1.シングルス、2.シングルス、3.ダブルス、4.シングルス、5.シングルスの順番で試合が行われるのだが、都道府県によっては、1番目と2番目にシングルスに出た選手はダブルスに出られないというルールのところもある。でもこのルールは非常にいい。1番目と2番目にシングルスに出た選手はダブルスに出られないということは、上手な子は4番、5番目に出ることになる。(一般的な話だがシングルスがうまい子はダブルスもうまいことが多い)。なので、各チームはエース級の選手は必然的に後半に出ることになり、実質的に実力勝負の様相を呈するようになり、オーダー表のある意味姑息な駒置き作業は必要がなくなるし、博打的な要素もなくなるのである。また後半に向かって試合は当然だが盛り上がっていくわけなのである。
しかし中学は6人定員なのである。なぜ4人ではなく6人なのかについては、話が長くなるので、すんません省略します。
つまり、我がチームはこの駒置きが上手になったのである。しかし決勝だけは、駒置きの考えすぎが裏目にでた。相手チームの老練な老監督の駒置き作業は娘っこ達が考えた浅知恵をいとも簡単に見抜いていたようだ。裏をかかれたのである。あきらかに向こう側の戦略勝ちである。対戦の組み合わせが分かった時、「あ やられたかな?」とも思ったのだが、対戦が始まり、ふたを開けてみると違った。組み合わせのハンディキャップをもろともせず比○中に勝利した。対局の不利を上回る程の実力の差を見せつけたのである。博打的な勝利でもなく、漁夫の利的な勝利でもない。実力で勝ち取った優勝ということになる思う。なので、心底、がんばった皆におめでとうを言いたい気持ちだった。
準決勝で勝った瞬間、その瞬間は全道のチケットをゲットした瞬間だった。そんな頃から、体育館の外は雪が降りはじめた。その後、決勝で勝った時分から大雪になった。自分は表彰式が終わった後、すぐ家に帰った。「自転車で来た娘は帰りどうするのだろう、この雪の中で帰れるのだろうか」と思いがよぎったが、子供たちで、ほっといても解決するだろう。オーダー表の提出と同じように、、、。そう思い、1人家路へ、、
しばらくして、友達の携帯電話を借りて娘がかけてきた」
「おと?」
「なした?」
「雪で帰れん!車で迎えにきてくれ!自転車も積んでってくれ!」
「OK,分かった!」
体育館まで、再度行く。玄関付近で、娘達が雪の中、寒そうに待っていた。車から降りて、娘達に近づいて行く。お父さんの性質からして子供達に、こう言いたくなった。
「お前ら、優勝したから、雪降ったし、って、笑うわ まじで、決勝で勝った時なんかさ、大雪に変わったし、究極のオチだわ。アハ」
というフレーズがのどまで出かかったのだが、今日くらいは下品なお父さんの性質は封印しようとブレーキをかけた。
「みんな がんばったね、よかったね。」という、「偽善者」という名札をぶらさげたようなセリフを吐く。その直後、雪はさらに強くなった。
後日、写真入りで、新聞のローカル版に掲載された。いつもは虫眼鏡で見なければならないほど小さな大会結果の文字に一喜一憂していたものだが、今回はたまたまかもなのだが、優勝記念写真をデカデカと掲載してくれた。新聞社さん、ありがとうございました。
写真は皆一様にピースサインをしている。
以前この中で1人、卓球部をやめると言い出した子がいた。皆困るので、大勢で説得してやめるのを思いとどまってもらったらしい(笑)。くやくてしょうがない涙を何度もボタボタ流した子もいるし、ファイナルセットで何度もディースを繰り返し、やっとこ勝利し、皆にもみくちゃにされたSちゃん。Sちゃんは絶対に泣かない子だと思っていたが、さすがにこの時は、万感余り、こみ上げてくる感情に勝てず、歩行が困難になるほどの嗚咽を見せてくれた。みんな、もし卓球部に入っていなかったら、こんなに泣いたり笑ったり怒ったり、ふてくされたり、よろこんだり、照れたり、ガッカリしたり、悲しんだりを経験しなかったのではないだろうか、写真を見ていてそんな風に思ってしまうのであります。
こう思います。
卓球とはメンタルな面が非常に強くそれと連動してる競技であること間違いなく、他のスポーツには無いそんな特長がそこにはあるのだと思うのであります。
試合が終わって対戦相手と握手する時、相手が手を出してきた瞬間こちらの手をすぐ引っ込めるような、そういう誠実でない選手が上まで勝ち進んでいく例をみたことがないし、負けたからといってラケットをぶんなげるようなことをする選手が上まで勝ち進んでいく例をみたことがないし、こちら側に間違って点数が入り、正直に申告しないでそのままとぼけて試合を続行するタイプの選手が上まで勝ち進んでいく例をみたことがないし、こちらの点数が有利になった瞬間に相手に対して横柄な態度になるタイプの選手が上まで勝ち進んでいく例をみたことがないし、言い訳するタイプの選手が上まで勝ち進んでいく例をみたことがないし、見栄っ張りなそんなタイプ、空気を読めないタイプ、人と仲良くできないタイプ、練習に遅刻しくるタイプ、ウソをついて練習をサボるタイプ、観覧席の友達に手を振って白い歯をみせる選手、相手が格下だと思うとバカにした態度で試合をするタイプ、わがままな子、友達を大事にできない子、イジメを看過する子、弱いものいじめをする子、人を仲間はずれにする子、人の悪口をいう子、人に心配させるタイプ、文句ばっかり言っているタイプ、思うようにいかなくて試合中イライラするタイプの選手。そんなこんなの選手が上まで勝ち進んでいく例を自分はみたことがない。
要するに君たちは自分の中にあるそんな未熟さをうまいこと克服するためにはどうしたらいいかを模索してきたから、だからここまでなんとかたどりつけたのであり、そんなステージまでなんとか来れたのではないかと、そう思うのであります。
だから賞状というのは未熟克服証明書みたいな意味合いがあるわけで、大人になっても未熟な人間が実はたくさんウヨウヨしていて、お父さんも実は偉そうなことが言えないのが残念なんだけれども、「結果が全てではない!」とか言うけれども、もちろん、結果は全てであるわけがないのだけれど、でも結果で全てを物語れるというそんな側面を持っていることも確かであって、どうかそんなことを分かって欲しいなぁと思うのですが、でも中学生にこんな話をしてもバカにされるだけなので、そんな思いもここで封印してみたいと思うのであります。
でもって、自分が知る限り、この写真に写っている選手の親はみな必死で生きているのを自分は知っています。必死で生きている親の子供さんたちがピースサインを放っているように見えてしまうのであります。うちの子もそうだが、みんな小学校の時、運動というカテゴリーで人に褒められることはなかったのではないかと思う。失礼だがそんな子達ばかりのような気がする。でも今、回りの人は皆君たちを褒めたくてしょうがない衝動にかられているのだと思う。うちの子もそうだが、中学に入った時、何か部活に入りたい。部活に入らなかったら友達が出来ないかもしれない、部活に入らなかったら殺伐とした不毛な学校生活になってしまうかもしれない、だから,だから、なにかの部活に入りたい、自分にも出来ることはなんだろう、自分でも出来ることはなんだろうという思いで胸を一杯にして、そんでもって、そんでもって卓球という地味な種目を選んだに違いないのである。それがどうだろう、下回転をかけてサーブを相手のショートフォに入れ、突っつきで浮いて帰ってくるレシーブボールを今度はこちらがフォアに回り込んでクロスに7割方の力のスマッシュを打ちこんでいくシステムプレー。わざと下回転をかけて少し浮かせて相手コートに返し、相手にスマッシュを意図的に打たせ、下回転がかかっているため、おそらくネットして墓穴を掘るだろうと見越し、でも間違ってこちらのコートに入ってきたら、一応レシーブだけできるようにしておく体制だけは整えておく詰め将棋のような誘いプレー。守備範囲の狭い選手に対してはオープンスペース、オープンスペースに対してボールを放ち、スペースがガラ空きになったら、そこではじめてスマッシュでポイントゲットに転じる忍耐的なボールコントロール。どの技も、気の遠くなるような回数の練習に裏打ちされていることを物語っている訳で、その昔、自分にも出来ることはなんだろうという思いで胸を一杯にして卓球部の門をたたいたあの当時の子供達とは思えない程のそんな君たちの成長ぶりに、心身ともに成長した成長ぶりかげんに対して舌を巻いておりますです ハイ。脱帽であります。ほんと脱帽なのであります。
写真の中の褒められ慣れていない子供達のピースサイン。そんなピースサインはいかにも自信なさげで弱々しさに満ちている。そう見える。しかし、こんな風にも見える。大げさかもしれないが、生きる力をやっとこ手にした、そんな記念写真に見えてしょうがないのである。お父さんがそんな記念写真に見えてしまうのはやっぱ年をとったせいなのか。焼きがまわってきたのか。
この写真を見ながら、お父さんはいつまでもお酒を飲んでいられた。いやー なんだか涙も出てくるし、ほとんどの子が小学生の頃から知っている子達だし、いろんなことを思い出してしまったりして、お酒がおいしくていおいしくてしょうがなかった。他の親御さんもきっと同じ思いなんだろうなぁと思うと余計お酒のピッチはすすんだ。
最後に先生にお礼を言いたいです。
部活の先生は大変です。いつも、この日も朝早くから夜まで、休日を返上して引率、指導していただき本当にありがとうございます。家庭を持っておられる先生にいたっては、かなり家庭を犠牲にしておられるのではないかと足を向けて寝れない気持ちでおります。先生方の愛情が子供を媒体にして伝わってきます。親にできることは、その愛情に対して、信頼でお返しすることだと思います。先生方の指導のおかげです。繰り返します。先生方の指導のおかげのそのたまものであります。心の中でただひたすら感謝の言葉をぶつぶつ念じております。皆さんご健康でありますように。ご家族が幸せでありますように。ご多幸に恵まれますように。いいことが沢山ありますように。