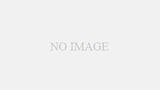もう去年の話なのだが、4年生の最初の参観日。娘が転校してきて最初の参観日だった。
教室の後ろの壁に4年2組の皆の作文が張り出してあった。テーマは「新学年になって」。共通して「何時に体育館に行って、それから始業式が始まって、そのあと校長先生のあいさつがはじまって」とか、小4らしい箇条書き風この上ない作文なのだが皆一様に「本日転校生が来た」ことに触れていた。
転校生とは娘のことである。
転校生はやはり子供達にとって一つのビッグニュースなのだろう。そして女の子約18人くらい中で4人の子の作文にこう書いてあった。
「今日転校生が来た。名前はユリッペ。ユリッペは私と友達になってくれるのだろうか?」
そう言った内容の子が4人ほどいた。
意外だった。
「転校生がやって来た」という時事的な話題ではなく、今度やってきた新人の子は自分と友達になってくれるかどうかに感心が置かれている。そんな子が4人だった。この4人の(いやもしかするともう少し人数が増えるのかもしれないが)子はもしかすると期待に胸膨らませて入学してきたのかぁ。沢山友達出来たらいいなぁと自分でも思い、回りの大人に「友達沢山出来たらいいねぇ」などというプレッシァーのような励ましに後押され、合うたびに「友達できたかい?」と聞く親戚のおじさんやおばさん。子供によってはそんな問いは陰惨な問いにしかならない訳で、もしかして脅迫にも似たそんな無神経な質問と戦うようにがんばってきたのだろう、「友達できたかい?」と聞かれて、「いない」と答える子供がいるだろうか?子供はそんな世界一カッコ悪い返事を死んでもする訳がないのに。子供によって、彼氏の居ない年頃の女性に「彼氏できたかい?」とか、結婚していない女性に「結婚した?」とかの、セクハラをいやがる女性に突き刺すナイフのような殺傷力を持っている。そういう子は「友達できたかい?」と聞かれて、「うん」と答える度 闇の中に落下していくのかなあと思う。親の手の届かない程、深い深い闇の底に急降下しながら そしてフェードアウトていく悲鳴を伴いながら。
そんな子供達が世の中にどれくらいるのだろう。
強迫観念のようにその質問に耳をふさぎたくなる子供達がいる。もちろんそうでない子供も大勢いる。でも我々大人は知らず知らず子供を追い詰めているのかもしれないとそう思った。
彼女達は上学年の間でかなわない思いの中 悲痛な3年間を過ごしたかもしれない。
転校生というのはもしかすると友達作りに失敗し夢敗れた子供達の敗者復活戦なのではないだろうか?転校生を紹介する先生の声はリングアナコールに聞こえるのかもしれないし、また、逆に「疲れを知らない子供のように」のフレーズの如く、年若なため いまだ絶望という概念を知らない子供のように、そのためチャンスだけ狙っている子にとってのつかの間の救世主に写るのかもしれない。そんな感じがした。そんな思いがした。そんな思いが作文に、箇条書き風の作文に本音が吐露されているように思われ、もっと言うとそれは悲鳴のような肉声やSOSにも受け取れる。
じゃぁどうすればいいのか?
その答えは残念ながら大人にないのだと思う。どうしてやることもできないのだと思う。子供達自身が答えを取りに行く以外ないのだろう。先生や親も含めて大人は残念ながら傍観するしかないのだとつくづくそう思う。
私おじさんは思う。
友達は一生で一人だけ作れるだけでいいんじゃないのか?おじさんはこの年になって思うのだが、友達が多いと豪語する人に限って実は敵が多い。友達が多い人間に限って何でも話せる友達は実は1人もいない場合が多い。よく「人間は一人では生きていけない」と言うけれど、だからなんなんだとつっこまれてそれでおしまいの話のような気がする。
じゃこう考えて欲しい。
「人間は友達がいなければ生きててもつらない」と、
同じ趣味や遊びを共有したり報告しあったりする相手がいなければ人生の大半は殺伐としたものになってしまうのだ。だから友達はいなくても生きていけるけど、でもいたほうが絶対的に人生は楽しいものへと変貌するんだ。友達を作り そしてその関係を持続させるためには、相手に合わせなきゃならなかったり、ある程度我慢も必要だし、時には相手の我がままも受け入れてあげなきゃならないし、コミュニケーションも上手でなけりゃいけないし、つまり忍耐力や許容力、説明力、説得力、包容力、理解力、いろんな総合的な力が必要だと言うことだ。小学校に上がる前に忍耐力や許容力という一つか二つだけの武器でいいから親がなんとかがんばって持たせてあげるだけで、子供は全く違う道を歩むことになると思うのだが、いかんせん、なにかの間違いでそのまま背中を押されて小学校という社会の縮図のような戦場に丸腰できてしまった子供達。君達はうっかりではすまされない保護者達の被害者なのか?さてでも、その力はどこでいったいどこで教えてくれるのか?それを全て教えてくれる魔法のような施設がやっぱり学校なんだと思う。そのために学校に行くのだと思う。立派な人になるために学校にいくんじゃなくて、ステキな友達関係を作る力を養うために学校に行くのだと思ってくれないだろうか。立派な人になるために学校に行くというのから離れて欲しい。たった一人でもいいから、なんでも話せる友達を作るため、そのための力を身につけるために、学校で読み書きを習ったりしてるという視点を少しでも取り入れて欲しいと思うんだが。方程式を解く能力は1つの能力でしかないんだけど、でも友達と喧嘩をしないで仲良く雑談できる能力の方が人間もしかしてとても大切な能力なのかもしれないよ。この年になっておじさんは特にそう思う。実はおじさんも何でも話せる友達ができないで困っていた時期があった。七転八倒してもだえ苦しんだ人には言えない暗黒の年月を持っている。でも経験上言わしてもらうと、友達が出来ないで悩んだ人間の方が将来とってもいい友達ができてるみたいだ。
だから今友達が出来ないといのはむしろ当たり前のことで、何も気にする必要はないのかもしれない。
でも自分で作文に「友達になってくれるだろうか」と表現できる能動性があるんだから、なんか問題の何割かが解決してるようにも思えるのだが。
というか友達が出来る日のカウントダウンが始まってるような気がするのだが。
話は変わるが、転校してきた初日、教室で皆の前で娘は自己紹介をした。「何々小学校から来ました」とかのお決まりの自己紹介。
突然担任の女の先生に「前の学校ではなんて呼ばれていたの?」
いきなり質問を振られた娘はとっさにこう答えたらしい。
娘「ゆ ゆ ゆりっぺ」って呼ばれてました。
先生「へー ゆりっぺ ってんだぁ じゃぁ ここでも ゆりっぺで決まりかな?!」
娘「あ はい アハ」
実は娘は前の学校では「ゆりっぺ」と呼ばれていなかった。
「ゆりちゃん」だった。
そう娘は嘘をついてしまったのである。しかし「ゆりっぺ」はその後この学校で定着してしまうことになる。1年半たった今も娘は「ゆりっぺ」と呼ばれている。娘の嘘は誠になったのである。
少したってから
父 「どうしてそんな嘘ついたの?」
娘「うーん 突然振られたのと、ゆりっぺって皆に呼ばれたい気がとっさにしたから」
父 「ふーん ゆりちゃんはいやだった?」
娘「そういう訳じゃないけど、ゆりっぺの方がなんかかわいいし」
父 「ゆりっぺっていう嘘がホントになっちゃうかもしれないけど 満足?」
娘「うん満足。でもちょっと後ろめたいかな? 嘘だから やっぱまずいかな?」
父 「いやまずくはないと思うよ、人を傷つけたりする嘘じゃないし それくらいの嘘ならお父さんもつくだろうし」
娘「ふーん」
父 「でも先生はそんな嘘を瞬間的に見破っていると思うよ」
娘「へ?」
父 「見逃してくれたんだよきっと」
娘「へ?」
父 「嘘ついて悪いと思うんだったら 見逃してくれたことに感謝すれば
んー いわゆるチャラになるかも」
娘「へ?ほんと?でも ばれたと思う?ホントにそう思う?」
父 「うん ばれたと思うよ。
それくらいの嘘を見破れなきゃ先生なんちゅー商売やってないと思うよ
他にも数人の子にばれてると思うよ」
娘「いやそれは絶対にないと思う まじで ないと思う!」
父 「あ そ」
それから数週間後、寝床についた娘が布団の中から、
娘「ねぇ おと 今日さぁーあ Sって子に言われた。」
父 「なんて?」
娘「ユリッペって前の学校でホントにユリッペって言われてたの? って」
父 「なんて答えたの?」
娘 「ギクっとしたさ で へ?う う う うん!」て答えた。
Sとは女の子なのだが、「ちゃん」を付けて呼ぶと怒られるらしい。自分の事を呼び捨てで呼ばなければいやがる子らしい。上学年くらいになるとそういう子がポツラポツラでてくるみたいだ。
こういう時、親がでしゃばるのはいい事だとは思わなかったが、でもここはなんだか肝心なところのような気がし、よせばいいのにでしゃばってしまった。
父 「その子と友達になれば?」
娘「へ?」
父 「そういう子と友達になればいいんじゃないの?」
娘「なんで?」
父 「君のうそを見破ったんでしょ? 感がいいんでしょ?要するに。」
娘「うん」
父 「そういう子と一緒に遊んだり行動したら楽しいし楽だよ」
娘「へ そうなの」
父 「うん そう思う。それにそういう子って仲良くなった子は絶対裏切らないだろうし、、、」
娘「なんで分かるの?」
父 「ほら 前の小学校にMちゃんがいたでしょ? あの子はクラスで一番感のするどい子だったしょ?それは君も認めるよね」
娘「うん 認める認める」
父 「Mちゃんて誰とでも遊ばなかったでしょ 特定の子としか遊ばなかったでしょ?どうしてだと思う?」
娘「分からん」
父 「ま お父さんの勝手な想像でしかないけど、感がするどいからさ、相手の嘘とか自慢とか見栄に敏感だからさ、相手の口から出てくる言葉に反応するんじゃなくて、相手が心の中で本当はどう思ってるかに、なんとなくかもしれないけど感応するからさ、だから口から出てくる言葉と心で思ってる事と食い違いがある場合、その食い違いの大きい子と話をするだけで疲れを感じるのさ、だから疲れない子としか遊ばなくなるんだと思う。」
娘「それって ウソとか自慢話しとかする子とは遊ばないってこと?」
父 「うん ま 簡単にいえばそうかな。ていうか、あの子のつじつまの合わない話し一度も聞いたことないし、てことはどんな小さなウソもつくのがいやなんだろうし、自慢話するのもいやなんだろうし、見栄張りったりするのもいやなんだろうし、あの年でめずらしくね。だからそうでない子とは逆にダメなんだと思う。君、結構、遊んでたよねMちゃんと?」
娘「うん」
父 「結構Mちゃんはうちに遊びにくるの楽しいみたいだったしょ?」
娘「てことは ウチがウソつかないから ってことだったの?ウチって偉いわけ?」
父 「ってことでもないと思うけど、実際君はうそついてる訳だし、ま、他に遊ぶ子がいなかったからしょうがなく君と遊んでいたのかもしれないし」
娘「ムカ」
父 「でも他の子に比べて口から出てくる言葉と心の中で思っていることの差が少なかったからじゃないのかな?遊んでも疲れない相手だと思われていたことは確かだと思うよ」
娘「ふーん」
父 「で 肝心な事だけど君はMちゃんのことが大好きだったよね、転校してきた今でもたまに遊んでるくらいだし」
娘「うん」
父 「つーことは、そういうタイプの子と相性が合うんじゃないの?」
娘「うんうん、なるほど、でもMちゃんって頭がいいってことか?」
父 「ま 良かったかもしれんけど、感がするどいのと学力は関係ないかも、感は今だけかもしれんし、でもMちゃんの親は大変かなぁ?」
娘「なんで」
父 「だって子供にどんな小さなウソもつけんだろうし、なんでも見破られるし、普通親は子供にウソついちゃダメとか言うけど、MちゃんちはどっちかというとちょっとくらいのウソはOKとか、少しくらいは許しましょうとか、そんなこと教えて緩和してあげなきゃMちゃん本人が苦労してしょうがないだろうし」
娘「ほうほう で Mちゃんどうなるの?」
父 「ま あそこの両親はとってもしっかりしてるし、そういうことはお父さんなんかよりよっぽどうまいこと子供に説明きるだろうし」
娘「へー で うちは感がするどい方なの?」
父 「ぜんぜ-ん!残念! 頭悪いし 頭弱いし」
娘「ム ムカリ、じゃなんで そういう子と友達になれと?」
父 「それは君が特殊な能力を持っているから」
娘「天才ということか?」
父 「そう君は人と喧嘩をしないと言う天才的な特殊な能力を持っているということだな」
娘「ということは天才が完璧ということか?」
父 「ということは天才ということでは全然ない」
娘「ヘ」
父 「前の学校のセンセも不思議がってた、なんで人と喧嘩しないんだろうか?気が弱いからなんだろか?とか、君はむかっ腹を立てたりしない人間らしい、それによってウサはたまらないんだろうか?たまったウサは発散できてるんだろうかって?」
娘「じゃやっぱ天才ってことじゃ」
父 「いや バカって方かなぁ」
娘「はぁ?」
父 「どっちにしても君は誰とでも仲良く出来るめずらしいタイプみたい」
娘「神様みたいにか?」
父 「いや 大阪商人みたいにだ」
娘「はぁ?」
父 「先生はそんな君を不思議がってたけど、お父さんから見ると全然不思議じゃなかった。」
娘「なんで?」
父 「ほら 君は店屋の子だったからだよ。お父さんとか商売やってる人と沢山接して育ったからだよ。お父さんはお客さんとか業者さんとかと喧嘩したことないでしょ、相手にどんな文句みたいなこと言われても、いろんな言葉を沢山ならべて機嫌よく帰すのうまかったでしょ、相手に合わせるのが割と上手だと思わん?商売人って割と皆そうなんだけど、お父さんは正しいとか正しくないとかという物事の考え方をほとんどしないでしょ。」
娘「じゃ悪いことしてもいいってことか?」
父 「そうじゃなくて それは善悪! 善悪とは違う、実ははずかしいことかもしれんけど、正しいとか正しくないとかというものさしは一つも持ってなくて、というか そんなものさしはどうでもいいと思っていて、かなり前にそんなもの捨ててしまっていて、それはけっしていいことじゃないんだけれども、でも相手が満足したかしなかったか、それだけのものさししか持ってなかったと思う。君はそんな親やまわりの環境で育てられたんよ。正しいかどうかの基準だとすぐ人と喧嘩になってしまうという虚しさを伴うんだけど、君はお父さんと同じで相手が満足したかどうかに感心が湧き、自分より相手が楽しかったかどうかの方が気になるのは、それはお父さんを見て育ったからだと思う。前の学校の先生に言われたことを、同じことをこっちの学校の先生にも言われたんだけど、君は自分というものを出さないらしい。人と口けんかすらしないらしい、しゃべってるよりほとんど相槌を打ってばかりいる子供らしい。だからといってストレスが溜まるって訳でもない、そんな君が小学生の先生からは不思議な動物に見えるんだと思う。」
娘「動物?」
父 「あ いや ごめん んー 小動物?」
娘「小動物?」
父 「あ いや ごめん ドーブツってのは先生が言ったんじゃなくお父さんが言ったんだけど、まとにかく、で、お父さんは なんで喧嘩しないと思う?」
娘「うーん? 喧嘩が弱いから?」
父 「ま 確かに喧嘩は弱いけど んー そうじゃなくて、相手の機嫌を損ねたらごはんが食べれんくなるからさ、だから人に合わせるのが習慣になってしまった。生きるためにそうなってしまったのさ」
娘「それって自慢か?」
父 「いーや でも人に合わせすぎて、自己主張するのがヘタなのも日本一位か二位なのさぁ、だからプラマイゼロなんだよね、人の顔色を伺ってしまう悲しい習性が、いやらしいほど身体に染み付いているともいえるんだ」
娘「.....」
父 「つまり君は誰とでも仲良くなれるんだよ つまりつまり、だから焦らんくても勝手に出来るからゆっくり友達作れば?ってことさ、どうせ時間かけて作るんだし、君にはある意味で、学校の先生も理解できないような人に嫌われない能力も備わっているわけだし、ホントに友達になりたい子を一本釣りにいけばいいじゃない」
娘「一本釣りってなんなんだ?」
父 「あ 釣っちゃダメだわ 「目指す」の間違えだわ」
娘「...」
父 「そんなこんなを踏まえて、Sと友達になれば?」
娘「ダメだわ Sは人気あるし、皆が友達になりたがってるって存在だと思うし」
父 「ありゃま そうか でもそういう子と友達になれる方法は一つだけあるかも」
娘「へ 何 何?」
父 「なんだと思う?」
娘「分からん」
父 「お父さんも実は分からん!」
娘が布団の中で大袈裟にバランスを崩して見せる。
娘「あ へ そうなの?」
父 「でもダメでもともとでいいんだったら ある!」
娘「だから なに?」
父 「ユリッペっていうウソをついたことを正直に打ち明けることだと思う。」
娘「へ?」
父 「ユリッペっていうウソをどうしてついてしまったかという心の中をむっちゃ正直に表現してみることだと思う。」
娘「えー!皆に対して」
父 「あ いや Sだけにさ」
娘「どうやって?」
父 「今度、それを打ち明けるにふさわしい時がもしかするとやってくるかもしれん、やってこなかったらそれでその子と縁がなかったと思って、ま、終わりだな、でももしそんなチャンスがやってきたら もうこんなチャンス来ないかもしれないラッキーだと思って、思い切って正直にどんな小さなウソもつかないで打ち明けてみたらは?」
娘「たとえばなんて言うの?」
父 「それは自分で考えんきゃ でも なるべく笑いをとる目的でネタとしてしゃべったらは?そういうの得意でしょ?」
娘「うん、でもネタって、ネタっていってもなぁ」
父 「だからホントはそんな嘘つくつもり全くなかったんだけど、でも、なんか追い詰められて、で、とっさに言ってしまって、次の日から、なんか嘘がホントになってしまった、小さな嘘が勝手に歩いてって、そんで大きなホントなっちゃって、で、いやーまいったぁ、みたいな」
娘「うーん」
と娘は考えこんでしまった。
娘「で、なんでそんなこと正直に言う? 嫌われるかもしれないじゃん、うそつきって?」
父 「だからいちかばちかだっての!そういう子は正直に言うと君にがぜん興味を持ってくれると思うよ、そういう子は皆にいじめられるような秘密を人に絶対ばらさんと思うよ、そういう子は正直にしゃべると、地獄の底でマリア様に会ったような顔すっから!少なくても嫌われたりいじめられたりすることだけはない、ぜってーだ!」
娘「おとうの読みが外れたらどうするの?」
父 「うーん、ま、すまんってとこかな?」
娘「それだけ?」
父 「それだけだけど、なにか?」
娘「...」
父 「ようするにお父さんは何が言いたいかって言うと、しゃべらなきゃバレないだろうと思ったら大間違いだってことさ。でもしゃべらなきゃバレないと思ってる人間が残念ながら大勢いる。ホントはそうじゃないのにだ、世の中には、大人になってもそれに気が付かない人が沢山いるのさ。そこに気が付いた人だけがホントの友達をつくれるんだと思うよ。クラスに必ずいるんよ、言葉でなく心に反応してくる人間が、前の学校のMちゃんがそうであり、この学校はSがそうなんだと思う。必ず小さい単位の人数の中に1人か2人いるんだわ。でもそういう子と友達になれたら、ほとんど言葉交わさなくてもお互い相手の考えてること分かようになるし、それってどういうことかって言うと、心が通じ合うってことだから、だからつまり絆が深いわけで、、、絆深いからホントの友達な訳で、、、眠たいから寝るわ、いい?寝ても?」
娘「最後に一ついい?」
父 「なに?」
娘「そういう子は感がいいからこっちの心が分かるかもしれんけど、こっちはどう?こっちは相手の心がわからんしょ?だって!? 友達って言える?それって?」
父 「たぶんそれは思いっきり大丈夫なんじゃないかと思う」
娘「なんで?」
父 「だって、そういう子だからこそ、言葉イコール心だも」
娘「あ」
父 「だからその子の心の中に近づきたければ、単純に言葉で質問すればいいだけじゃん、でも君がどんなちいさなウソも見栄もかなぐり捨てながら、その子に接するということが、絶対条件になるけどね。で、そういう子は何でも正直に話す子をどういう風に評価すると思う?」
娘「...」
父 「やさしいと評価してくれるんじゃないかな」
娘「なんで?」
父 「だって自分を疲れさせないし、自分を傷つけないし、ほっとさせてくれるし、安心させてくれるし、つまりだから正直に接する君を絶対に売りはしないよ!いいようにしか思ってくれないから大丈夫なんだってばさ!転校してきたばっかで、いちかバチかの勝負に出るのはいやかもしれんけど、ま、決めるのは君だ、お父さんは関係ないので、寝るわ! じゃーねぇ」
「うん」と答えた娘の声は涙混じりで布団の中で篭りぼやけた楽器の音のように聞こえた。
ちょっと娘には残酷な話だったかな、それと大分何かに偏った話でもあるな、思い込みで一杯しゃべっちまったな、それにしてもお父さんのしゃべり、なんか、なめらかだったような。一方でかなり間違った事教えてるような気もしたが、ま、いいか。うちの子だし。ま、しょうがないかな。しょうがねーよな。勘弁してね。
それから1ヶ月後くらいだったと思う。
寝る時、布団の中から娘が
娘「ねぇ、おと、今日さぁーあ、あのこと言ったさ」
父 「へ、 何? 何を?」
娘「はら、あれさァ、ユリッペって、うそ言ったこと、Sと同じ班になったんだよね、今日沢山話す時間があったし、で、Sに言ったさホントのこと」
父 「へ? ホントに言った? お前、アホか? アホなのか? ホントに言ったのか?」
娘「おとうが言えって言ったじゃん、何それ!」
父 「そうかもしれんけど、ホントに言うかフツー?」
娘「何なんだよ、それって!」
父 「言ってしまったか?終わった事はしゃーないしゃーない、んで、どんな反応だった?」
娘「ひ ひぇえぇぇぇーーええーー!」とか言われた。
父 「そっか、そっか、そっかぁ、んで、嫌われたか? ん? みたいだか? ん?」
娘「いや、それはないと思う。」
父 「皆にばらされると思うか? ん?」
娘「それは絶対ないと思う!」
父 「つーことはとりあえず良かったみたいって感じか?」
娘「うん、そうかもしれんわ」
父 「ほうら、んじゃお父さんの言った通りになったベー!」
娘「全然違うんじゃねーのかー!」
それから数ヵ月後娘はSとよく遊ぶようになった。
お父さんも休みの日は運転手をやらされ、3人でプールに行ったり、サイクリングにいったり、ゲーム場にいったり、いろんな公園にいったり。娘はSと友達になれたかに見えた。娘はその子と遊ぶ時とても楽しそうだったが、しかしその子は娘をどう見ただろう。お父さんの見たところ、娘が持っている心の寂しさみたいなものをとてもよく理解してくれ、それを埋めてくれようと一生懸命娘に合わせて遊んでくれるような子だった。
こんなやさしい子が世にいるのか?と感動するほどである。
この子と遊べは娘の心は100%満足するだろう、でもこのSという子は満足だろうか。娘には悪いが、この子の心を満足させるための人間のいろいろを残念ながら娘は持っていないような気がした。お父さんの目にはそんな風に映った。根拠は特に無い。なんとなくだ。Sは小児麻痺の同級生の子を毎日送り向かいしたりしている。放課後は車椅子の後ろを押していろんなところへ遊びに連れていったり、話し相手になったり。そんなことを何年も続けている。Sもたよられている、Sなしでは学校生活を送れないという子がいるのである。Sの献身的な気持ちは にわかボランティアのそれではない。自分自身の方に愛情が傾いてしまっているきまぐれな人間によくある偽愛でもない。献身してそして頼られることが何よりの甲斐であるように、Sは無私になることがまるで喜びであるかのように小児麻痺の子といつも一緒にいる。
つまりSと娘とは人としての格が違うのだ。(笑)
そんな神々しい子を娘はいきなり1本釣りに行ってしまったのである。そんな娘のおっちょこちょい加減に閉口というか脱帽というか。
やっぱり娘はアホだった。
Sはとても人気のある子供らしかった。
しかしSが特定の子とばかり遊ぶと、嫉妬して自分の身体を傷つける子がいることを娘は後日知ることになる。Sは心に闇を持った子とも向き合ってきた。娘にとってそれはあまりに重たいテーマだった。そのため娘のハイテンショナルな友達に対する思いは一瞬で興ざめしてしうことになる。娘は愕然となり自重するようになった。そのため遊ぶのはたまにって感じになった。
その後、娘の友達作りの壮大な計画は5年生になりクラス替えによってリセットされることになる。Sとは別々のクラスになった。自然接触は少なくなり、遊ぶことはごくまれな社交辞令に風化していった感だ。
でもこう思う。
娘はいい経験をしたのではないだろうか。
うそが一人で怪物のように歩き出してしまったこと。そのウソをきっかけにその反対側にある正直さがいかに扱いにくいものであるかということ。正直に生きるって、それはとても険しく厳しい道のりであるということ。正直さは幸か不幸かの思いもよらない結果をもたらしてくれるということ。お父さんは頼れるようで実は頼れない存在であるということ。
4年生の終わり頃、クラスに転校生がやってきた。男の子だ。その日転校生というのはやはりビックニュースらしく娘は布団のなかで、
娘「今日吉田っていう名前の男子の転校生がきたさ」
父 「また先生に 「前の学校でなんて呼ばれてたの?」って聞かれた?」
娘「うん、聞かれてた!」
父 「なんて言ってた?」
娘「「よっしー」 って言われてました っていってたかな?」
父 「んじゃ、その よっしー って言葉すんなり出てきたみたいだかい?」
娘「うーん、いや、そういえば 「えーと」とか言ってちょっと考えてから出てきたかな?」
父 「それって転校してきた時の君と同じじゃん?」
娘「へ」
父 「その子、よっしー って呼ばれてたんじゃなくて、よっしー って呼ばれたいってことなんだよきっと、前の学校では、そうだなぁ、よっちゃん、だったとか?誰かさんと同じだよね、それって!」
娘「あ」
父 「どうしてSが君のウソを見破ったかというと、言葉がすんなり出てこなかったことに単純に違和感を覚えたからだよ、きっと、今日の「よっしー」ってのに君が違和感を覚えたように」
娘「あ」
父 「つまりタネを明かせばなんのことないって感じだろ、Sは霊能力のような感のするどさを持ってる訳でもなんでもなくて、普通の人が聞き流してしまうことでも、それを違和感として捕らえることができるということなんだと思う。でもそれはそれで特殊な能力だと思けど、そういう子のことを、ま、いわゆる感がいい子って言うんだと思うけどね」
もしかするとこう思った。
娘はなぜとっさに「ゆりっぺ」と答えてしまったのだろう。
ひょっとすると娘は今回のこの転校をきっかけに自分自身を変えたいと思っていたのだろうか。昔の自分に別れを告げたかったのだろうか。だから「ゆりっぺ」と呼ばれる環境は彼女にとって必須だったのかもしれないし、一世一代の大博打に打って出たとしてもなんだかうなずけてしまう。
新しい名前から自分をリセットさせたかったのかもしれない。
それにしても子供に「前の学校でなんて呼ばれてたの?」と突然質問を振る先生。
もしかするとこの先生はそんなことを全てお見通しなのではないだろうか。
少しでも自分を変えたいという意識を持った子へ、きっかけを振ってくれているのかもしれない。転校生に新しい自分をスタートさせる手助けをしてくれているのかもしれない。先生なりの転校生に対するささやかなプレゼントなのかもしれない。
娘の断片的な報告の言葉を頼りに、目をつぶり、今日やってきた転校生と先生のやり取りを想像してみた。
「前の学校でなんて呼ばれてたの?
ん? 何? よっしー?
へぇー! よっしー ってんだぁ
じゃ! この学校でも よっしー で決まりだね!」
先生の声が 先生のエールに聞こえる。
我々親や社会の人間は学校の先生のことをあまり良く知らない。しかしところどころ散りばめられた先生の愛情はステキでとても深い。我々がその愛情を認識できる能力を失った時、この社会は闇の方角へ向かう。親が隠された愛情にそっと耳をすませたりする、そんな協力的な気持ちを失った瞬間、その瞬間から親や子供の心に怪物が宿るのではないだろうか。